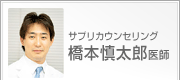
1994年 金沢大学医学部卒業同年、金沢大学医学部産婦人科入局、医局人事で多数の病院に勤務し、産婦人科、美容皮膚科領域の研究及び臨床経験を積み2000年に大名町スキンクリニック開院
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本補完代替医療学会・幹事
日本産婦人科学会・正会員
日本医学脱毛学会・正会員
日本美容医療協会・準会員
マンモグラフィー読影認定医
介護支援専門医
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
産婦人科医でありながら美容クリニックの院長も務める橋本医師。また、健康食品・化粧品・整体・鍼灸など補完代替医療も探究し、西洋医学だけでは難しい未病(病気ではないが、健康ともいえない中間の症状)を防ぐ医療に力をそそいでいる。
サプリメントは、足りない栄養素を補うものです。その中でも人間が健康に生活するために必ず必要な栄養素【必須栄養素】を学びましょう!
味覚の正常化や皮膚・粘膜の機能維持等の作用があります。
亜鉛(Zn)を多くとる場合は、ビタミンAも多めにとると、相乗効果でそれぞれの働きがアップします。
亜鉛が多く含まれる食べ物
牡蠣、レバー、するめ、うなぎ、豆類 等
EPA(イーピーエー)はエイコサペンタエン酸の略語です。
DHA同様 血液の流動性を高め血管を拡張させて血小板凝集を抑制します。
また血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らして善玉コレステロールを増やす働きがあります。
EPAが多く含まれる食べ物
さば、まいわし、さけ 等
カリウムは生命活動を維持する上で重要な役割をしているミネラルです。
カリウムとナトリウムは体内において常にバランスをとりながら作用します。
カリウムは筋肉でエネルギーづくりに働いているので、不足すると筋肉の動きが悪くなり、力が出なくなります。
特に血圧においては、ナトリウムが血圧を上げる作用をもつ一方で、カリウムは血圧を下げる働きがあります。
カリウムが多く含まれる食べ物
茎わかめ、大豆、バナナ、かつお、じやがいも 等
骨や歯を構成するほか脳のはたらきにも関与する重要な必須ミネラルのひとつです。
カルシウムは神経伝達物質にも大きな影響を与え、興奮や緊張を緩和し、イライラをやわらげる作用もあります。
また血中のカルシウムが不足すると骨から貯蔵カルシウムがとり出され、不足分をカバーしようとします。この状態が続くと骨がもろくなります。
マグネシウムやビタミンDは、カルシウムの働きに関与したり吸収を助ける作用があるので、カルシウムを摂る際は一緒に摂ると効果的です。
女性は出産で多量のカルシウムを失い、加えて更年期を過ぎると、骨の成長を促すホルモンであるエストロゲンの分泌が低下し、一気に骨がもろくなります。
そのため、成長期にしっかりカルシウムを摂って運動をしましょう。
カルシウムが多く含まれる食べ物
牛乳、プロセスチーズ、モロヘイヤ、ししゃも、木綿豆腐 等
糖質や脂質の代謝を促進するミネラルです。
クロムが多く含まれる食べ物
玄米、ひじき、うるめいわし、あさり、切干大根 等
食物繊維(ファイバー)は、ヒトの消化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総称です。
一般的な働きとしては、ブドウ糖の吸収速度をゆるやかにして、腸管内の有害物質の排出、便をやわらかくする、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えるなどがあげられます。
食物繊維が多く含まれる食べ物
おから、納豆、ごぼう、板こんにゃく、しいたけ 等
発育と生殖に欠かせないミネラルの中の必須元素の一つで、「セレニウム」とも呼ばれています。
セレンの代表的な働きは、体内に出現した余分な活性酸素を除去する抗酸化作用です。この抗酸化作用は、非常に強くビタミンEの50~100倍とも言われています。
魚介類が嫌いな人、野菜しか食べないといった極端な偏食や無理なダイエットをする人などは、セレンが不足します。
セレンが多く含まれる食べ物
いわし、牡蠣、牛もも肉薄切り、ねぎ、玄米ごはん 等
DHAはドコサヘキサエン酸の略語です。
日本人になじみの青魚に多く含まれています。脳や神経組織の発育、機能維持に不可欠な成分で、人間のからだでは脳細胞に多く存在します。
DHAは記憶や学習能力の向上や、EPAと同様、血液の流動性を高め血管を拡張させて血小板凝集を抑制します。
また血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らして善玉コレステロールを増やす働きがあります。
DHAが多く含まれる食べ物
まぐろ、ぶり、さんま、さけ 等
鉄は、赤血球が酸素を運搬するのを助ける必要な栄養素です。しかし吸収率が約8%前後ときわめて低いために欠乏しやすいミネラルです。
鉄分が不足すると貧血を引き起こす要因となります。
貧血は無理なダイエットをしてる人、妊娠中の人、インスタント食品をよく食べる人に多く見られます。
鉄分が多く含まれる食べ物
レバー、牛もも肉薄切り、かつお、小松菜、納豆、ひじき 等
銅はミネラルのひとつで、最近になり栄養機能食品の栄養成分として追加されました。
鉄を赤血球の構成要素であるヘモグロビンに変換するのにかかせないミネラルです。
そのほか多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける働きがあります。
銅が多く含まれる食べ物
するめ、ほたるいか、牛レバー、アーモンド、ココア 等
ナイアシンは、糖質、脂質、タンパク質の代謝に不可欠な水溶性のビタミンで、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
飲酒習慣がある人は積極的にとるとよいでしょう。
ナイアシンが多く含まれる食べ物
たらこ、鳥胸肉、落花生 等
パントテン酸(パントテンサン)はビタミンB群の仲間です。
体内では、コエンザイムAという補酵素の一部として働き、脂質、糖質、タンパク質の代謝に働きます。 そのほか、副腎皮質ホルモンなどの各種ホルモンの働きにも関与します。
パントテン酸が多く含まれる食べ物
鶏レバー、子持ちかれい、納豆 等
ビオチンはビタミンHとも呼ばれ、パントテン酸と共に酵素を作り、脂肪酸やコレステロールの代謝をしながらエネルギーを作り出す働きをしています。
生卵を好んで摂取したり、長期間にわたって抗生物質を摂取している場合は、胃や腸の中でビオチンの吸収を阻害されます。
ビオチンが多く含まれる食べ物
レバー、卵黄、落花生 等
皮膚や粘膜、髪、眼の働きを正常に保つ、肺や気管支などの呼吸器系統の病気の感染に対して抵抗力をつける、生殖機能を維持する、成長を促進するといった働きがあります。
ビタミンAが不足すると皮膚がかさつき視力や免疫力の低下などが起こります。
コンピューターを使うしごとをしている方は特に視力の低下を防ぐために食生活に注意しビタミンAを摂取するようにしましょう。
ビタミンAが多く含まれる食べ物
牛レバー、バター、うなぎ、ニンジン、カボチャ、のり、わかめ 等
ビタミンB1は糖質を分解する際に補酵素として必要で、別名「糖代謝ビタミン」とも呼ばれています。
お酒をよく飲む人はB1が不足しがちとなり糖質が分解できず、乳酸などの疲労物質がたまるため疲れやすくなります。
2週間もビタミンB1が不足する食生活を続けていると、疲れやすい、食欲不振、むくみ、動悸、気分がふさぐ、集中力の低下が起こります。
米食の日本人には最も不足しやすいビタミンといえますので、継続的に摂取することが必要です。
水溶性のビタミンで、熱に弱く調理による損失は30~50%。煮汁に溶け出るので汁ごと食べるとよいでしょう。野菜はぬか漬けにするとB1が増えます。
ビタミンB1が多く含まれる食べ物
豚肉やレバー、豆類、玄米、牛乳 等
ピンク色の結晶であることから「赤いビタミン」としても有名です。
悪性貧血は赤血球が減ったり、巨大な赤血球ができたりすることから起こりますが、ビタミンB12を摂取すると赤血球のヘモグロビン合成を助けられるため簡単に良くなります。
B12が不足して悪性貧血になると、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれなどを感じます。
また、神経過敏になったり、ふさぎこんだり、記憶力や集中力が減退したりと、神経や精神症状にも影響があります。
ただし、微生物の働きによっても合成されるため、納豆、味噌、醤油などの発酵食品には含まれています。
ビタミンB12は、調理過程で70%ほどが損失しますが、これは分解ではなく、肉汁等で流出するためです。
ビタミンB12が多く含まれる食べ物
肉、レバー、魚、貝類、乳製品 等
ビタミンB2は特に、脂肪の代謝には欠かせないビタミンです。
ビタミンB2は水溶性のビタミンで、酸や熱にはやや安定していますが、アルカリや光には弱い性質を持っています。体内にためておけないので毎日摂るのがよいでしょう。
ストレスの多い人、脂質の摂取量が多い人などは不足に気をつけましょう。
ビタミンB2が多く含まれる食べ物
レバー、青魚、緑黄色野菜、乳製品、卵、納豆 等
皮膚炎を予防することから発見されたのがビタミンB6。ピリドキシンとも呼ばれ、タンパク質の代謝には不可欠で、肉や魚をたくさん食べる人は、B6の必要量も増します。
免疫機能を正常に維持する働きも持っており、B6が不足するとアレルギー症状がでやすくなります。
また、不足すると神経過敏、不眠、口内炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、湿疹、虫歯、貧血にもなりやすくなります。
妊娠中はホルモンの関係で需要が増し、欠乏しやすくなります。
ビタミンB6が多く含まれる食べ物
カツオ、マグロ、サンマなどの青魚、肉 等
健康に欠かせないビタミンCですが、いろいろと弱点も持っています。
ビタミンCの弱点1・「熱に弱い」 加熱すると簡単に分解してしまいます。
ビタミンCの弱点2・「水に弱い」 水に溶けやすいので、洗うとどんどん減ってしまいます。野菜や果物を長く水にさらしておくのはやめましょう。
ビタミンCの弱点3・「空気に弱い」 空気に触れるとどんどん酸素を取り込み、分解されてしまいます。
ビタミンCの弱点4・「体から排出されやすい」 2、3時間で体外に排出されてしまいます。一度にたくさん摂取するより、こまめに摂るほうがいいようです。
ストレスやたばこ、飲酒などでも大量に消費されてしまう点も、ビタミンCの弱点です。
ビタミンCが多く含まれる食べ物
果物、野菜、いも類 等
カルシウムやリンの吸収を促すなど、丈夫な骨や歯を作るために必要な働きがあります。
発育期の子供はもちろん、妊娠、授乳期、更年期の女性は特に、カルシウムと共にしっかりと摂取する必要があります。
ビタミンDが不足すると、いくらカルシウムをとっても吸収が上手くいかず、発育不全や骨粗鬆症などの原因につながります。
紫外線に当たることによって皮膚で合成されるので、普段から日光に当たっている人はビタミンD不足を心配する必要はあまりありませんが、日光に当たる機会の少ない人は食事やサプリメントから摂るように心がけると良いでしょう。
ビタミンDが多く含まれる食べ物
鮭 ちりめんじゃこ さんま カツオ マグロ しいたけ きくらげ(乾) 等
抗酸化作用をもつ脂溶性のビタミンです。体内では活性酸素により生体膜や細胞膜の不飽和脂肪酸が酸化され、過酸化脂質ができます。
これが増えると体の機能が低下し、病気や老化現象が進行します。
ビタミンEは脂溶性で熱や酸では強く、鉄やアルカリ、紫外線などに弱い性質です。
ビタミンEが多く含まれる食べ物
アーモンドなどの種実類、カボチャ、ホウレンソウ 等、野菜などは油で炒めて食べると吸収力がアップします。
ビタミンKは、出血した時に血液を固めて止血する因子を活性化する役割をします。
また、骨の健康維持にも不可欠で、骨にあるたんぱく質を活性化し、骨の形成をうながすことも知られています。このため、ビタミンKは骨粗しょう症の治療薬としても使われています。
ビタミンKは腸内細菌によってもつくられますし、いろいろな緑黄色野菜に多く含まれるため、通常の場合は不足する心配はありません。
ビタミンKが多く含まれる食べ物
小松菜、ホウレンソウ等
プロテインは、主に筋力の増強やたんぱく質の補給等を目的としたたんぱく質を原料としたサプリメントです。
筋肉、臓器、皮膚、毛髪、爪はもちろん、血液、代謝反応に不可欠な酵素、一部のホルモン、免疫の抗体、遺伝子など、すべての細胞原形質はたんぱく質を主材料として作られています。
プロテイン(タンパク質)が不足すると、スタミナがなくなったり、病気への抵抗力がなくなったり、脳の働きが鈍ったり、子どもでは発育障害が現れます。
プロテインが多く含まれる食べ物
かつお、豚もも肉薄切り、卵、プロセスチーズ、大豆 等
代表的な抗酸化成分でビタミンEやビタミンCより強い作用を持っているとされています。
摂取されたベータカロチン(カロテン)は必要に応じて体内でビタミンAに変化します。
ビタミンAに変わるのは必要量(摂取量の1/6)だけで、残りは、ベータカロチン(ベータカロテン)のまま、体内で生じる活性酸素をつかまえて消去する働き(抗酸化作用)をします。
ベータカロチンが多く含まれる食べ物
かぼちゃ、にんじん、モロヘイヤ、ひじき、ほしのり 等
骨や歯を構成するほか脳のはたらきにも関与する重要な必須ミネラルのひとつです。
カルシウムは、体内では99%が骨や歯に、残りの1%が血液などの体液や筋肉組織にあります。
ストレスの多い人、激しい労働をする人、お酒をたくさん飲む人、胃腸などに慢性的な疾患がある人、高齢者、妊婦、授乳婦、加工品や清涼飲料水をたくさんとる人は、マグネシウムの不足を招きがちです。
牛乳などをよく飲む人も、カルシウム摂取量に比例した量のマグネシウムが必要です。
マグネシウムが多く含まれる食べ物
アーモンド、干しひじき、豆腐 等
カルシウム、鉄分、亜鉛、銅、カリウム、マグネシウムがミネラルである。
からだの機能の維持や調節には欠かせない微量栄養素です。
ミネラルは、骨格を形成する、体液の酸度や浸透圧を調節する、酸素の補助因子やホルモンの成分になる、神経や筋肉などの機能を維持する働きがあります。
ミネラルが多く含まれる食べ物
こんぶ、豚レバー、モロヘイヤ、大豆、アーモンド 等
葉酸(ヨウサン)はビタミンB群の仲間です。
葉酸はビタミンB12と同様、造血ビタミンとして必要な栄養素の一つです。特に妊娠中や授乳期の女性では、葉酸を補うことが重要です。
また、お酒を大量に飲む人、アスピリンや避妊薬のピルを飲んでいる人も欠乏しやすくなるので、十分な摂取を心がけましょう。
葉酸が多く含まれる食べ物
鶏レバー、枝豆、モロヘイヤ 等
細胞の細胞膜を構成している成分で、脳にいたっては40%も含まれています。
この細胞膜は、血管を通ってくる血液中の栄養分と酸素を細胞内に取り入れる働きをします。
皮膚から、毛根、目の中、脳、内臓、すべて細胞で構成されており、レシチンは、生命の基礎物質です。
レシチンが多く含まれる食べ物
卵黄、大豆、納豆、豆腐、ピーナッツ 等